御岩神社に「呼ばれる」という言葉には、なぜか「特定の人だけが導かれるように」感じる、不思議な響きがあります。
まるで神さまが、静かに「今ですよ」と合図を送ってくれているようです。
この記事では、その「呼ばれる感覚」の背景や、古くからの信仰に込められた意味をたどりながら、実際に訪れるときに心を整えるためのポイントを、お伝えしていきます。
御岩神社が放つスピリチュアルな魅力、ご利益、そして“光の柱”として語られる神秘的な現象や、ゼロ磁場の存在に惹かれる方も多いでしょう。
また、御朱印の見開きやお守りの人気の理由、ブレスレットに宿るエネルギーの意味、さらには「登山がきつい」といわれるその理由や、安全に参拝するためのヒントにも触れていきます。
このガイドでは、過度な神秘化や断定を避けながら、歴史と信仰、そして「神さまとのご縁」を尊重し、安心して御岩神社を訪れるための、実践的で温かな道しるべをお届けします。
なぜ御岩神社に呼ばれると言われるのか
御岩神社 スピリチュアルな魅力とは
光の柱が示す神秘的な現象について
ゼロ磁場どこにあるのか詳しく解説
御岩神社 危険とされる理由と注意点
御岩神社 登山 きついと感じる人への対策
御岩神社 スピリチュアルな魅力とは

御岩神社は、茨城県日立市の御岩山全域を神域とする、日本でも有数のスピリチュアルスポットです。
古くから山岳信仰の中心として尊ばれ、修験者たちが心身を鍛えた修行の場でもありました。
この地では「山そのものが神」とされ、訪れる人々は自然の呼吸に溶け込み、心と体が洗われるような感覚を味わいます。
御岩神社には、国常立尊(くにのとこたちのみこと)をはじめ、大国主命、伊邪那岐尊・伊邪那美尊など、日本神話を形づくる神々が祀られています。
さらに、御岩山全体に188柱もの神々が鎮まると伝えられ、宗派や信仰を超えて祈りを受け入れる“開かれた聖域”でもあります。
楼門や三本杉、斎神社の天井画などに残る神仏習合の名残は、祈りと芸術が交わる美しい証といえるでしょう。
参拝者が「呼ばれる」と感じるのは、心の静まりと自然の響きが重なるとき。
山道を歩くうちに音が消え、木漏れ日や風が体のリズムを整えてくれる。
その穏やかな環境が内なる声を呼び覚ますのです。
心理学的にも、森林浴や歩行瞑想は副交感神経を整えると報告されています(出典:環境省『自然と健康の関係に関する調査報告書』https://www.env.go.jp/)。
こうした要素が「呼ばれる感覚」を支えているのでしょう。
御岩神社には、「形より心を大切にする」という風土があります。
手水舎での清め、鳥居での一礼、参道を歩くときの慎み。
その一つひとつが、見えない存在への祈りの表現です。
静かな時間を大切にしながら歩くことこそ、この場所に導かれた意味なのかもしれません。
歴史と環境がもたらす没入感
御岩神社周辺からは縄文時代の祭祀遺跡が見つかっており、太古の人々もこの地を聖なる場所として崇めていたことがわかります。
『常陸国風土記』にもその名が記され、古代から霊山として人々の心を支えてきました。
参道には樹齢数百年のスギやヒノキが並び、訪れる人を包み込むように立っています。
春の新緑、秋の紅葉と、四季の移ろいごとに表情を変える景観は、五感すべてに語りかけてくるようです。
足音や風の音に耳を傾けて歩くと、日常の時間がゆるみ、心が自然と「いま」に戻っていく。
それはまさに、自然と一体になれる祈りの時間です。
光の柱が示す神秘的な現象について
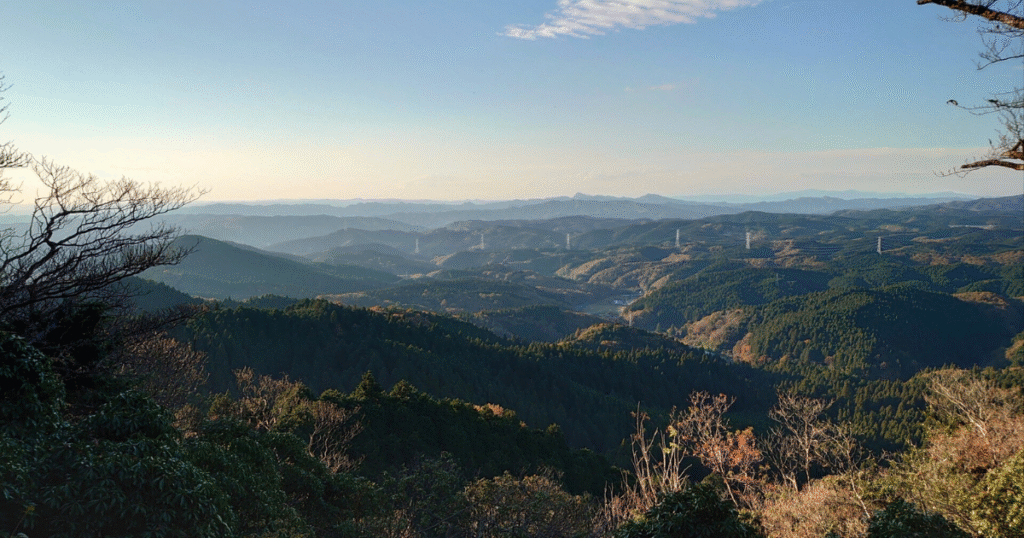
御岩山の山頂付近では、「光の柱」と呼ばれる現象が語り継がれています。
宇宙飛行士が「御岩神社の上空に光の柱を見た」と語った逸話が広まり、全国的に知られるようになりました。
この現象は、科学的には「太陽光の屈折」や「大気中の氷晶による光柱(サンピラー)」として説明されています。
気象条件が整うと、朝や夕方に太陽の光が氷の結晶に反射して垂直の光となり、天へと伸びるように見えるのです。
御岩山の標高や湿度、風の流れが、この幻想的な光を映し出す舞台をつくっています。
一方で、信仰の世界では光は「神の御霊の現れ」や「導きのしるし」として語られてきました。
仏教や神道においても、光は悟りや覚醒を象徴する存在。
御岩神社で語られる「光の柱」は、その自然と信仰が交わる場所にふさわしい象徴なのです。
訪れる際は、奇跡を求めるよりも「自然の中に神を感じる心」で向かいましょう。
祠や石柱には手を触れず、写真撮影は節度を守ることが大切です。
この山がいまも清らかに保たれているのは、ひとり一人の敬意の積み重ねによるものだからです。
ゼロ磁場どこにあるのか詳しく解説
御岩神社についてよく聞かれるのが、「ゼロ磁場はどこ?」という疑問です。
地球の磁力線が交わって打ち消し合う地点を「ゼロ磁場」と呼び、その場に立つと心身が整うとされています。
御岩山も、長野県の分杭峠などと並び注目されてきました。
多くの人が“感じる場所”として語るのは、山頂付近の石柱の背後や、斎神社から少し登った小祠のあたり。
ただし、磁場は地中の鉱物や地層の影響を受けるため、常にゼロになるわけではありません。
御岩山には花崗岩や雲母片岩が多く、磁力線を偏らせるため、測定結果や体感に差が出ることもあります。
また、森林の湿度や気温の変化が呼吸や感覚に影響を与えることも知られています。
酸素濃度が高まることで心が落ち着き、体のリズムが整うこともあるでしょう。
そうした自然との共鳴が、「磁場が整うように感じる」という体験を生むのかもしれません。
科学的な定義にとらわれるよりも、御岩神社を「自然と人が調和する場所」として感じるのがこの地らしい姿です。
石を持ち帰ることや掘削は文化財保護のため禁じられています。
測定器を使う場合も、周囲の人や自然への配慮を忘れずに。
御岩神社のゼロ磁場は、数値で測れるものではなく、人と自然の“響き”が交わる神域。
その調和を心で感じ取るとき、あなた自身の中にも静かな光が生まれていくでしょう。
御岩神社 危険とされる理由と注意点

御岩神社は「日本最強のパワースポット」として知られ、多くの人々が祈りを捧げに訪れる場所です。
けれどもその神域は、豊かな自然とともに“山”というもう一つの顔を持っています。
森の静けさの裏には、天候の変化や道の険しさといった、自然の厳しさが潜んでいるのです。
御岩山へと続く登山道は、整備されていない箇所が多く、木の根や岩が入り組む急斜面が続きます。
雨のあとには苔や泥が滑りやすくなり、軽装での入山は非常に危険です。
御岩神社の公式案内でも、雨天や積雪時の入山禁止、午後以降の登山制限が明記されています。
これは、山中の光が弱まり、足元が見えづらくなることで事故のリスクが高まるためです。
信仰の地である前に、ここは「生きた自然」であることを、心に留めておきましょう。
気象と時間帯
御岩山は標高530mほどの山ですが、太平洋の湿った風の影響を受け、天気が急に変わることがあります。
梅雨や秋の長雨の時期には、わずか数分で霧が立ちこめ、視界が10メートル以下になることも。
午後3時以降の入山を制限しているのは、そうした突発的な霧や暗転を避けるためです。
特に下山時に日が落ちると、林の中はすぐに暗くなります。
ヘッドライトを持っていても、足元を正確に見極めるのは難しくなります。
そのため、登る前には必ず最新の天気情報を確認し、境内の掲示板の注意書きをチェックしましょう。
スマートフォンのアプリだけでなく、紙の地図や携帯ライトを用意しておくと安心です。
冬の時期は、雪がなくても道が凍っていることがあります。
軽アイゼンやトレッキングポールを使うことで、転倒のリスクを大きく減らせます。
山を敬うことは、自然を敬うこと。安全を守る装備もまた、一つの祈りの形です。
マナーと禁止事項
御岩神社の山は、古代から「神の御心が宿る場」として守られてきました。
そのため、参拝のマナーを守ることは、神さまへの敬意を示すことでもあります。
境内や山中での植物・石の持ち帰り、火の使用、飲酒や食事はすべて禁止です。
これらは自然の命や文化財を傷つける行為につながるため、慎む必要があります。
また、ペットの同伴も認められていません。
野生の生態系を守り、神域の清らかさを保つための大切な決まりです。
トイレは限られているため、出発前に済ませておくのが安心です。
写真撮影をする場合も、儀式や他の参拝者が写り込まないように注意しましょう。
拝殿や祭祀中は撮影が制限されていることが多いため、社務所の案内に従うことが大切です。
御岩山の静けさと秩序を守ること――それが、最も美しい参拝の姿です。
御岩神社の山道は、自然そのものが生きています。
自分のリズムで巡るなら、レンタカーでの旅が心地よいですよ。
日立周辺で借りられるレンタカーを探す
御岩神社 登山 きついと感じる人への対策

御岩山は標高こそ高くありませんが、実際に登ると想像以上に体力を使います。
勾配の急な場所が多く、木の根が複雑に絡んだ道ではバランス感覚も必要になります。
雨上がりや冬場は特に滑りやすく、下山時に脚の疲れを感じやすい傾向があります。
無理をせず、途中の斎神社などを折り返し地点にする判断も大切です。
登山をする際の基本装備として、次のようなものを整えておくと良いでしょう。
- 足首をしっかり支えるトレッキングシューズ
- 吸湿速乾性の高いウェア(綿素材は避ける)
- 薄手のレインウェア(急な雨への備え)
- 帽子・手袋・軽量リュック
水分補給は30〜40分ごとを目安に行い、塩分もこまめに取りましょう。
また、御岩神社の公式案内では、山中での飲食を控えるよう呼びかけています。
それは、神域の清らかさを守るためであり、野生動物との共存を保つためでもあります。
以下は主要ルートの比較です。難易度や所要時間を把握したうえで、体力や天候に応じて適切なルートを選択してください。
| ルート名 | 距離 | 累積標高 | 参考コースタイム | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 御岩神社~御岩山 往復 | 約3.3km | 約293m | 約1時間40分 | 初心者に最適な往復ルート。参拝と登山を両立できる |
| 御岩山~高鈴山~神峰山 周回 | 約10.4km | 約734m | 約5時間06分 | 眺望と達成感を味わえる。中級者以上向け |
| 日立アルプス 周回 | 約23.3km | 約1,256m | 約8時間45分 | 体力と経験を要するロングコース。縦走愛好家に人気 |
| 向陽台~御岩山 往復 | 約4.7km | 約325m | 約2時間20分 | 稜線側から登る静かなルート。人混みを避けたい人向け |
登山の基本は、「時間」「装備」「体調」の3つの管理です。
初めて訪れる方は、午前中に登り始め、昼過ぎには下山する計画を立てましょう。
焦らず、ひとつ一つの呼吸とともに歩みを進めることで、山のエネルギーと調和できます。
御岩神社の登拝は、挑戦ではなく「対話」です。
自然と自分を感じながら、穏やかな時間の流れに身をゆだねる。
その体験こそが、御岩山が授けてくれる最大のご加護なのかもしれません。
泊まりでゆっくり参拝したい方はこちらから周辺宿をチェック!
\ 周辺の人気ホテル・宿泊施設をチェック! /
御岩神社に呼ばれる人が知るべき体験とご利益
ご利益で知られる御岩神社の信仰背景
御岩神社 ブレスレット 効果と意味
御岩神社 お守り 人気の種類と特徴
御朱印 見開きの魅力と入手のポイント
御岩神社 呼ばれる人へのメッセージとまとめ
ご利益で知られる御岩神社の信仰背景

御岩神社は、茨城県日立市の御岩山を神域とし、古代から人々の祈りが絶えない霊地です。
縄文時代の遺跡が発掘され、『常陸国風土記』にもその名が記されていることから、この地が太古より「天地とつながる場所」として崇められてきたことが分かります。
御岩山全域には188柱もの神々が鎮まると伝えられ、国常立尊をはじめ、大国主命、伊邪那岐尊、伊邪那美尊など、
天地創造に関わる神々が一堂に祀られています。
それはまるで、日本という国の「はじまりの祈り」が凝縮された神域のようです。
中世以降は修験者が修行を行う霊場として栄え、江戸時代には水戸藩の祈願所として徳川光圀公(黄門様)も参拝したと伝わります。
この頃、社殿の整備や寄進が進み、地域の信仰と文化の中心として発展しました。
御岩神社のご利益は、開運招福・厄除・家内安全・交通安全・学業成就・良縁など、日常生活をまるごと支える“調和と再生”の祈りに根ざしています。
けれど、それは「願いを叶えてもらう」ことではなく、「神とともに生きる」ことを教えてくれる信仰です。
心を正し、日々の行いを整える――
その姿勢の中に、御岩の神々のご加護が宿るのです。
参拝の際は、鳥居の前で軽く一礼し、拝殿では二拝二拍手一拝を丁寧に行いましょう。
境内では静かに、木々や石にも敬意を払いながら歩くこと。
御岩山そのものが御神体です。
自然と対話するように、一歩ずつ進むことが、神々との縁を深める道になります。
現代では、心や体を整えるために訪れる人も増えています。
“ゼロ磁場”として知られる御岩山のエネルギーを感じ、「心が軽くなった」「流れが整った」と語る人も少なくありません。
けれどもその体験は、科学よりも“感受の祈り”によって生まれるもの。
大切なのは、自然と調和する心で訪れることです。
御岩神社の信仰は、「神・自然・人の調和」という日本古来の精神を今に伝えています。
手を合わせ、自分の内側と向き合うとき、その静かな時間こそが、最も深いご利益となるでしょう。
御岩神社 ブレスレット 効果と意味

御岩神社で授かるブレスレットは、“身につける祈り”としての意味を持ちます。
一本ずつ祈願のもとに作られ、持つ人の心を清め、日々の思いや行動を整えるための道具として授与されています。
その効果は「願いを叶える力」ではなく、「願いを忘れずに生きる意識」を支えることにあります。
ブレスレットが手首に触れるたびに、神前で誓った思いを思い出し、自らを律する「祈りのスイッチ」となるのです。
心理学でも、触覚によって意識を切り替える働きは知られており、これは「アンカリング効果」として説明されています
(出典:文部科学省『人間の行動科学に関する研究』https://www.mext.go.jp/)。
素材にも意味があり、水晶は浄化と再生、翡翠は繁栄と平和、黒曜石は魔除け、瑪瑙は調和と結びつきを象徴します。
石の組み合わせによって、持つ人のエネルギーを整える意図が込められています。
扱う際は、神聖なものとして丁寧に扱うことが大切です。
長時間の水濡れや直射日光を避け、使わないときは布袋や箱に納めましょう。
それは、神さまから授かった光を守る行為でもあります。
ブレスレットは「持つためのもの」ではなく、「気づくためのもの」。
身につけるたびに、自らの在り方を見つめ直す――
その時間こそが、御岩神社のブレスレットがもたらす真の「効果」です。
御岩神社 お守り 人気の種類と特徴
御岩神社のお守りは、全国でも屈指の種類を誇ります。
開運、厄除、交通安全、学業成就、良縁、家内安全――
どれも現代を生きる人の願いに寄り添い、神職による祈祷を経て授与されています。
意匠には、御岩の象徴である「龍」や「杉」が多く、白や金を基調とした布地に清らかな力強さを感じます。
社紋を織り込んだ刺繍や、三本杉をモチーフにしたお守りも人気です。
どれも「自然と神話が息づくデザイン」として、手にした瞬間に清らかな気が流れます。
授与を受ける前には、拝殿で手を合わせ、感謝の祈りを。
お守りは「買うもの」ではなく「授かるもの」。
心を整えて受け取ることで、神気がより穏やかに宿ります。
持ち歩くときは、財布や鞄の中の清潔な場所に納めましょう。
スマートフォンなど電磁波を発するものとは分けるのが望ましいです。
そして、一年を目安に新しいお守りへ。
古いものは感謝の言葉とともに神社へ返納し、お焚き上げをお願いしましょう。
お守りを持つことは、神に頼るというより、自分を律するための約束でもあります。
「守られているからこそ、今日を丁寧に生きよう」――
そんな意識が、最も美しいご利益を生むのです。
御岩神社の公式ブログで御守りの一部紹介がされています。

御朱印 見開きの魅力と入手のポイント
御朱印は、神社に参拝した証として授与される、墨書と朱印が一体となった“祈りの印”です。
御岩神社の御朱印はその中でも特に格式が高く、筆致の力強さと構図の美しさが際立っています。
なかでも人気なのが「見開き御朱印」。
2ページいっぱいに広がる墨の流れと朱印の配置は、まるで神職の祈りが紙の上に舞い降りたよう。
一文字ごとに神聖な気配が宿り、見る人の心に静かな響きを与えます。
御岩神社では、通常の拝殿の御朱印のほかに、祭礼や特別な行事の際だけ授与される「限定御朱印」もあります。
正月や例大祭(5月頃)には、特別な見開きデザインが頒布されることもあり、その日参拝した人だけが授かれる貴重なものです。
また、斎神社や天之御中主神を祀る摂社など、複数の御朱印をいただくことで、御岩山全体の信仰の流れを記録として残すこともできます。
授与は社務所にて行われ、受付時間はおおむね午前9時から午後4時まで。
土日や祝日は混み合うため、時間にゆとりをもって訪れるのが安心です。
御朱印帳は自分で持参しても構いませんが、御岩神社オリジナルの朱印帳は、龍や御岩山を描いた美しい意匠が人気で、記念に授かる人も多いようです。
見開き御朱印の一番の魅力は、神職の祈りそのものが筆に宿っているという点にあります。
墨の濃淡や朱印の重なりには、一つとして同じものがなく、それぞれが唯一の「御神気の証」。
だからこそ、御朱印は集めるためのスタンプではなく、神と人とを結ぶ“記憶のかたち”なのです。
拝受する際は、必ず拝殿での参拝を終えてから社務所へ。
御朱印をいただいたあとは、朱印帳を丁寧に閉じ、折れや汚れを防ぐよう大切に扱います。
御朱印に刻まれるのは、神さまの印だけではなく、あなたがその瞬間に捧げた祈りの記憶。
それは、御岩神社の信仰と芸術、そしてあなた自身の「心の軌跡」をつなぐ一枚なのです。
御朱印の情報については、こちらをご参照ください。

御岩神社(おいわじんじゃ) 基本情報
| 住所 | 〒311-0402 茨城県日立市入四間町752 |
| アクセス | 上野方面から常磐線を利用 → 日立駅下車 → バス(東河内行き、御岩神社前下車)約35分 タクシー:日立駅から約20分 常磐自動車道「日立中央IC」から約10分 また、三郷ICから常磐道経由だと約1時間30分(途中日立中央IC経由) |
| TEL | 電話:0294-21-8445 |
| 参拝時間 | 参拝時間:6:00〜17:00 登拝時間(山道を歩く時間帯):6:00〜15:00 社務所受付:9:00〜17:00 |
| 駐車場 | あり(無料) ・駐車台数:15台+33台+25台+120台(複数の区画がある) ・第1駐車場の利用時間:8:00〜18:00(令和7年4月1日より) ・※三が日(1月1〜3日)は第1駐車場が閉鎖され、第2~第4駐車場や臨時駐車場が使われることあり |
| 公式HP | 御岩神社 |
御岩神社 呼ばれる人へのメッセージとまとめ
- 御岩神社 呼ばれる感覚の背景は、歴史と自然環境が調和した神域の特性によって育まれてきたもの
- 188柱の神々を祀る信仰伝承が、多様な人々の祈りや願いを時代を超えて受け止めてきた歴史を持つ
- スピリチュアルな語りは、信仰を支える礼節や参拝作法の意識を高めるための重要な枠組みとなる
- 光の柱は神秘的な逸話として知られ、現地では静寂と敬意をもって参拝する姿勢が求められている
- ゼロ磁場どこという疑問は、地質や測定条件の違いにより数値や体感が変わる現象として理解される
- 触れてはならない祠や石柱への非接触の配慮が、信仰対象を守り後世に伝えるための保全意識となる
- 雨天や積雪時の入山禁止など、安全確保と環境保護のための基準を遵守することが参拝の前提となる
- 午後の入山制限を踏まえ、日没前に下山できるよう工程を逆算し無理のない参拝計画を立てることが重要
- 御岩神社 登山がきついと感じる場合は、体力に合わせて短時間で往復できるルートを選択するのが賢明
- 登山装備はトレッキングシューズや雨具、水分補給を基本に安全を最優先とした行程を組み立てること
- お守り人気は開運や厄除など生活に寄り添う祈願を自分の目的に合わせて選ぶ視点を持つと効果的
- ブレスレット効果は霊的効能ではなく、祈念を日々思い出し行動を正すための象徴として理解される
- 御朱印の見開きは授与期間や祭礼時期により異なり、現地の案内を確認して受けるのが望ましい
- 写真撮影は参拝者の妨げや儀式の支障とならぬよう、常に信仰行為を優先する意識を忘れないこと
- 御岩神社 呼ばれる感覚は、礼節と感謝を忘れず自然と神々に心を寄せる姿勢から生まれるもの

